
先日、久しぶりに献血へ行ったら、楽しみにしていたお菓子のセルフサービスがなくなっていて驚きました。「献血のお菓子が廃止されたって本当?」「一体なぜ?」と、同じように感じている方も多いのではないでしょうか。実はこの変化には、衛生管理意識の高まりといった現代的な理由だけでなく、日本の血液事業が乗り越えてきた「売血」という歴史的な背景も深く関わっています。
この記事では、献血のお菓子がなくなった理由から、現在の献血で受けられるサービス、そしてかつて存在した報酬制度の問題点までを詳しく解説します。なぜお菓子が提供されていたのか、という素朴な疑問から、安全な血液を支える「無償の原則」の尊さまで、スッキリとご理解いただけますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 献血のお菓子が廃止・変更された具体的な理由
- 現在の献血で受けられるサービス内容
- 過去に存在した「売血」制度とその問題点
- 報酬がないのに献血が行われる本来の意義
献血のお菓子廃止はなぜ?その背景と現状
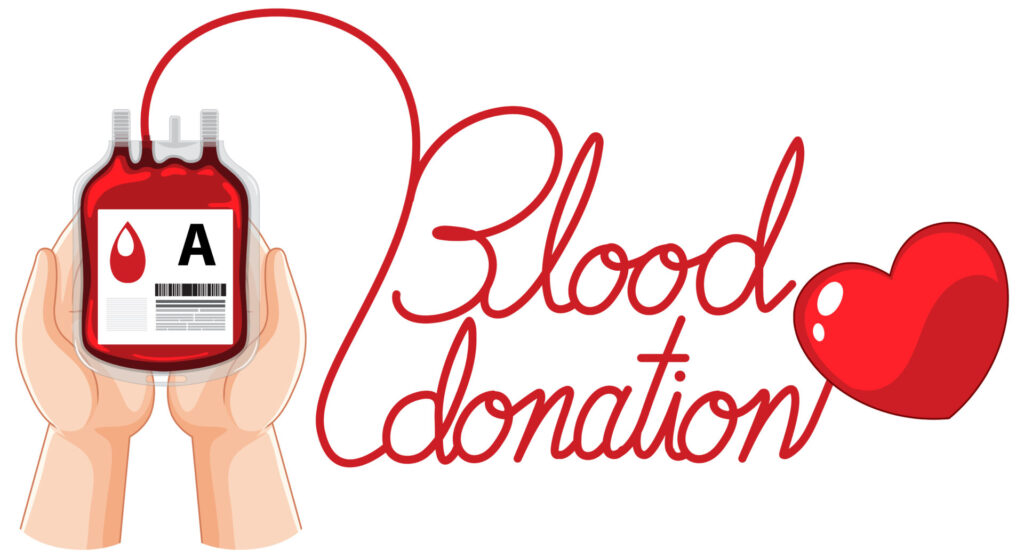
- なぜ献血をするとお菓子がもらえるのですか?
- かつて献血は「お菓子食べ放題」だった?
- 献血がお菓子目当てという声もあったのか
- 運営方針の変更による提供内容の変化
- 大阪など一部ルームでの提供終了事例
なぜ献血をするとお菓子がもらえるのですか?
献血後にお菓子が提供されるのには、単なるサービス以上の、献血者の体調を気遣う医学的な理由がしっかりと存在します。献血によって体内の血液量が減少すると、身体は一時的に循環血液量が不足した状態になります。これにより、血圧が低下しやすくなるのです。
特に、献血後に急に立ち上がったりすると、脳への血流が一時的に不足し、めまいや吐き気、失神といった「血管迷走神経反応(VVR)」と呼ばれる症状を引き起こすことがあります。これを予防するためには、十分な休息と水分・糖分の補給が極めて重要です。
お菓子は、速やかに吸収されて血糖値を上昇させるのに適しており、献血による身体への負担を和らげ、体調を安定させる効果が期待できます。つまり、お菓子の提供は、献血という善意の協力をしてくれた方々の安全を第一に考えた、大切なケアの一環だったのです。
補足:水分補給も重要
お菓子だけでなく、献血ルームで飲み物が自由に飲めるのも同じ理由です。血液の約半分は「血しょう」という液体成分で、その大部分は水分です。失われた血液量を補い、血液の粘度を下げて流れをスムーズにするためにも、献血前後のこまめな水分補給が強く推奨されています。
かつて献血は「お菓子食べ放題」だった?

はい、以前は多くの献血ルームで、セルフサービス形式による「お菓子食べ放題」が実施されていました。献血を終えた人が休憩スペースで、数種類のお菓子を自由に選んで食べられるスタイルは、献血の魅力の一つとして広く認知されていたようです。
インターネット上の体験談などを見ると、クッキーやせんべい、チョコレート、ご当地限定のお菓子などがバスケットに盛られ、リラックスした雰囲気で休憩時間を過ごせたという声が多く見られます。このような心遣いは、注射への緊張感を和らげ、献血への心理的なハードルを下げる効果がありました。また、休憩スペースが献血者同士のちょっとした交流の場となり、「また来よう」と思わせるリピーター確保の一因になっていたことは想像に難くありません。
献血がお菓子目当てという声もあったのか
献血の動機は人それぞれですが、「お菓子が目当て」という声が一部であったことは事実です。特に、充実したお菓子や飲み物のサービス、場所によってはアイスクリームの自動販売機などは、献血に行くささやかな楽しみとして捉えられていました。
もちろん、多くの人は輸血を必要とする誰かを助けたいという純粋な社会貢献の気持ちから献血に協力しています。しかし、その善意の行動にプラスアルファの魅力があることで、「どうせならサービスが良いところで」「買い物のついでに寄ってみよう」と、献血への一歩を踏み出すきっかけになっていた側面も否定できません。この「お菓子目当て」という動機は、結果的に献血者数を確保する上で有効な副次的効果を持っていたと言えるでしょう。しかし、あくまで献血の本来の目的は、病気やけがの治療のために血液を必要とする患者さんを救うための、善意の行動であることは忘れてはなりません。
運営方針の変更による提供内容の変化
近年、長年親しまれてきたセルフサービスのお菓子提供を見直す動きが全国的に広がっています。この背景には、社会情勢の変化に伴う、主に2つの理由があると考えられます。
1. 衛生管理意識の高まりと感染症対策
最大の理由は、衛生管理と感染症対策です。不特定多数の人が同じ容器のお菓子に手を伸ばすセルフサービス形式は、接触感染のリスクが避けられません。特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、社会全体の衛生意識が飛躍的に高まったことで、この形式を維持することが困難になりました。
2. 食品ロス削減への取り組み
もう一つの理由は、食品ロスの削減です。SDGs(持続可能な開発目標)への関心が高まる中、食べ放題形式ではどうしても発生しがちな残りや廃棄が問題視されるようになりました。貴重な資源を無駄にしないという観点から、運営コストや環境への配慮も含め、必要な分だけを提供する形へとシフトが進んでいます。
現在の提供方法
こうした理由から、現在ではセルフサービスを廃止し、献血を終えた一人ひとりに個包装のお菓子や栄養補助食品を手渡したり、アイスクリームの自動販売機で使える専用コインを渡したりする形式に変更する献血ルームが増えています。これにより、衛生的で無駄のない提供が可能になっています。
大阪など一部ルームでの提供終了事例
運営方針の変更は全国的に見られますが、特に具体的な動きがあったのが大阪府の献血ルームです。日本赤十字社の運営方針変更に伴い、段階的にサービスの提供が縮小・終了しました。
| 提供終了日 | 終了したサービス内容 |
|---|---|
| 2023年3月31日 | コイン式自動販売機によるお菓子の提供 |
| 2024年3月31日 | アイスクリームの提供 |
このように、お菓子だけでなくアイスクリームの提供も終了し、現在は飲み物のみの提供となっている場合があります。サービスの有無や内容は、地域や献血ルームによって異なるため、献血に行かれる際は、事前に日本赤十字社の公式サイトで最寄りの献血ルームの情報を確認することをお勧めします。
献血のお菓子廃止と報酬をめぐる背景

- 献血をするといくら謝礼がもらえるのですか?
- 現在は献血で何ももらえないのが原則
- かつて存在した「売血」という制度
- 売血行為がはらんでいた道徳的な問題
- 飲み物や記念品がもらえるケースも
献血をするといくら謝礼がもらえるのですか?
結論から明確に申し上げると、現在の日本では、献血をしても現金による謝礼は一切もらえません。これは、日本の血液事業が、世界保健機関(WHO)も推奨する「自発的で無報酬の献血(Voluntary, Non-remunerated Blood Donation)」という基本理念に基づいているためです。
献血は、あくまで見返りを求めない自発的な善意によるボランティア活動と位置づけられています。もし献血にお金が支払われるようになると、経済的に困窮している人が生活のために健康を害してまで無理な献血を繰り返したり、感染症のリスクを正直に申告しなかったりする可能性があります。こうした事態を防ぎ、安全で質の高い血液を安定的に確保するため、無償での協力が世界的な原則となっているのです。
現在は献血で何ももらえないのが原則
前述の通り、献血は無償のボランティアであるため、金銭的な対価は支払われません。お菓子や飲み物の提供は、あくまで献血後の体調管理と、協力へのささやかな感謝の気持ちを示すためのサービスの一環でした。
そのため、運営方針の変更によってお菓子の提供がなくなったとしても、献血の本来の価値や意義、尊さが変わるわけではありません。輸血を待つ患者さんの命を救うという、献血の最も重要な目的は、サービスの有無にかかわらず、決して揺らぐことはないのです。
「何ももらえないなら、献血する意味がない」と感じる人もいるかもしれません。しかし、見返りを求めない多くの善意によって支えられているこの「無償」の原則こそが、日本の現代の輸血医療の安全性を根底から支えている、非常に大切な考え方なのです。
かつて存在した「売血」という制度
実は、日本でも1960年代までは「売血」という制度が広く行われていました。これは、民間企業が運営する「血液銀行」が、お金を支払って人々から血液を集め、それを保存して医療機関に供給するという商業的な仕組みです。
当時の新聞記事によると、1964年頃の売血の価格は400ccあたり1200円ほどだったとされています。当時の国家公務員の初任給が約14,000円だったことを考えると、これは日々の生活の足しになる、決して安い金額ではありませんでした。そのため、学生や日雇い労働者などが、お金を得る手段として売血を行っていました。
売血がもたらした深刻な問題
しかし、この売血制度は深刻な社会問題を引き起こしました。お金ほしさに身分を偽って短期間に何度も売血する人が後を絶たず、そうした人々の血液は栄養状態が悪く「黄色い血」と揶揄されました。さらに、輸血を介した肝炎などの感染症が蔓延する大きな原因となり、多くの患者さんが被害を受けました。この問題の重大さを社会に知らしめたのが、1964年に起きた「ライシャワー事件」です。当時の駐日米国大使が刺され、輸血を受けた際に輸血後肝炎に感染したこの事件は、血液事業のあり方を根本から見直す大きなきっかけとなりました。(出典:厚生労働省 薬事・食品衛生審議会血液事業部会 資料)
売血行為がはらんでいた道徳的な問題

売血には、前述した健康上のリスクだけでなく、倫理的・道徳的な問題も指摘されていました。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授が著書『それをお金で買いますか』の中で言及しているように、人間の身体の一部である血液を市場で売買の対象とすることには、社会のあり方を揺るがす根源的な問題が潜んでいます。
主な問題点は以下の通りです。
1. 貧困層からの搾取と健康格差
生活に困窮している人々が、健康を害するリスクを承知の上で、生活費のために自らの血を売らざるを得ない状況が生まれます。これは、経済的な弱者から一方的に搾取する構造であり、健康格差を助長するという強い批判がありました。
2. 善意や利他主義の精神の衰退
血液がお金で取引される「商品」になると、「困っている人を助けたい」という純粋なボランティア精神や利他主義が社会から失われる危険性があります。人々は献血を「お金が必要な人がやる仕事」と捉えるようになり、「私の仕事ではない」という意識が広がってしまうかもしれません。このように、市場原理が導入されることで、本来尊いとされるべき道徳的な責任感が締め出されてしまうのです。
これらの深刻な問題を受け、日本では国民的な議論の末に売血制度が廃止され、安全な血液を確保するための「無償献血」へと大きく舵が切られました。
飲み物や記念品がもらえるケースも
献血では現金がもらえないのが原則ですが、協力への感謝を示すために、飲み物以外のものがもらえる場合もあります。
多くの献血ルームでは、献血後も休憩スペースでジュースやお茶、スープなどの飲み物が無料で提供されています。これは、前述の通り、献血後の体調管理のために水分補給が不可欠だからです。
また、献血への協力回数に応じて、オリジナルの記念品が贈られる「複数回献血クラブ」などの制度があります。これは日本赤十字社が定めているもので、継続的に献血に協力してくれている人への感謝のしるしです。内容は時期や地域によって異なりますが、グラスやお皿、タオルといった実用的なアイテムが用意されていることが多いようです。時には、人気キャラクターとのコラボレーショングッズがもらえるキャンペーンが実施されることもあります。
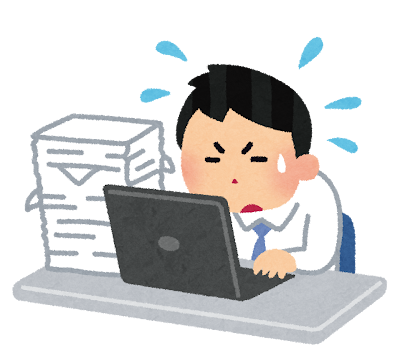
まとめ:献血のお菓子廃止と今後の動向
今回の記事の要点をまとめます。
- 献血後のお菓子提供は体調安定という医学的理由があった
- かつてはお菓子食べ放題で献血の魅力の一つだった
- 近年は衛生管理意識の高まりや食品ロス削減のため提供方法が変化
- 個包装のお菓子を手渡したり専用コインを渡す形式が増加
- 大阪府など一部地域ではお菓子の提供自体が完全に終了
- 献血に行ってもお菓子がもらえないケースは今後も増える可能性がある
- 献血は無償のボランティアであり金銭的な謝礼は一切ない
- 無償の原則はWHOも推奨しており安全な血液確保に不可欠
- 日本では1960年代まで商業的な「売血」制度が存在した
- 売血は輸血による感染症拡大や健康被害など深刻な問題を引き起こした
- 血液の売買は貧困層からの搾取や道徳観の喪失といった倫理的な問題もはらんでいた
- 数々の問題の反省から現在の安全な無償献血体制が確立された
- お菓子がなくても体調管理のための飲み物は提供されることが多い
- 献血回数に応じてオリジナルの記念品がもらえる制度もある
- 献血のお菓子廃止は時代の流れでありサービスの有無で献血の本来の価値は変わらない
